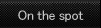|サイトマップ|文字サイズ ![]()
![]()
![]() |
|
青木冨美子のオフィシャルサイト
ワインの知識
海中で発見されたシャンパンが話題になっていましたが、映画『グラン・ブルー』にも海の中でシャンパンを開けるシーンがあります。 水中で開ける時はどんな感じなのですか?
鉄含有量の少ないワインを購入したいのですが、参考にすべきものは何かあるのでしょうか?
ワインのボトルはボルドー、ブルゴーニュで異なり、例えばカリフォルニアでもぶどうの種類によりほぼこれを踏襲しているようですが、ボトルの形にはどういう意味あるいは効果があるのでしょうか?
昨年、メルシャンの勝沼ワイナリーで「きいろ香2007」のマグナムサイズを購入したのですが、このワインはいつ飲むのがベストでしょうか?
1980年代までは「若いボルドーワインにインクとか墨のような香り」を感知するものが良く見られました。 これは《メトキシピラジン》という化合物の臭いで、緑色を呈した未熟な果梗に由来します。 晩熟のブドウ品種であるカベルネ・ソーヴィニヨンを主原料とするボルドーワインにしばしば感知され、 《ブルーブラックのインクの匂い》といわれ、1990年代前半までは、その存在はカベルネ・ソーヴィニヨンの品種特性香と認識され、 欠陥臭とされていませんでした。 しかし、ブドウ栽培技術の進歩により、果梗が褐色になる状態まで健全にブドウを完熟させることが可能となり、 1990年代後半からは《メトキシピラジン》の匂いはカベルネ・ソーヴィニヨンの品種特性香ではなく、 未熟臭の一つと位置付けられるようになりました。 《メトキシピラジン》の臭いは、貴説のとおり、空気に触れることにより消滅することはありません。 最近では、圃場における果房の選別作業を徹底したり、色彩判別装置を装填した除梗機を採用し未熟な果梗と不良果粒を除去したり、 白色のベルトコンベアー上で目視により緑色の果梗と不良果粒を除去することが広く行われています。 なお、《メトキシピラジン》は加温により分解します。 主として早飲み赤ワインや廉価な赤ワインの醸造法である「除梗破砕後の発酵前のマストを約75℃に昇温させる加温醸造法ThermovinificationやフラッシュデタントFlash Détente」を 採用すると、未熟な果梗が混入しても《メトキシピラジン》の臭いを感知することはありません。 「熟成したワインに、《メトキシピラジン》臭がしない」というのは、そのワインの醸造にあたり、圃場で《完熟した果房》を収穫し、長期熟成に耐えるワインに仕上がっていたためと思われます。
回答者:戸塚昭ページのTOPへ戻る
官能評価にかかわる問題は、質問者と回答者が同じ席で同じものを口にしていない限り、正確な情報を伝えられません。 以下、私(戸塚)の憶測です。 失礼な言い方になりますが、日本市場に流通した80年代のシャンベルタンは「高温劣化」したワインがほとんどです。 高温劣化に伴い、種子由来の、一般にタンニンといわれている分子量約35,000の《プロアントシアニジン》は小さな分子量のポリフェノールに変化し、 荒々しい渋味が張りのない渋味となるとともに、酸味を構成する有機酸はアルコールと結合してエステルとなり酸味が減少します。 「真昆布と本枯節の出汁」とのことですが、塩あるいは醤油により《塩味》が付与されていませんか。 本来、フランス料理と赤ワインのマリアージュは、カルシウムとマグネシウムの含有量の多い《岩塩》が仲人役(牧師役)を務めるのですが、タンニンの渋味の少ないワインでは 「海塩」でも相性が良くなります。旨味に及ぼす塩味の効果については、ここで申し上げるまでもないと思います。 ということで、柔らかな落ち着いた渋味に、出汁の隠し味である「塩(塩化ナトリウム」)が出汁とワインの調和に効果を及ぼしたものと考えられます。 いずれにしろ、料理(女性名詞)とワイン(男性名詞)の《結婚》は《鹽梅(あんばい)》が重要であり、料理が勝っているうちは、ワインは特徴のない《水(ドイツ語では中性名詞)》となり、 ワインはなんとなく「スイスイ」と飲めてしまいますが、ワインが料理に勝ってしまうと、両者の結婚は《破談・離婚》へと進行します。
回答者:戸塚昭ページのTOPへ戻る
ブルゴーニュも、2007や2008は酸が高い年ですね。 最近ブルゴーニュに行く機会がありましたが、2007、2008とも、フレッシュでミネラル感のある、すばらしい白ワインだと思いました。 十分な酸がある分、熟成もきくと思います。 2009のフランス白ワインは、ヌーヴォー以外まだ見る機会がありませんが、暑い年だったので酸は穏やかなんでしょうね。 コーヒー香の質問ですが、 コーヒーのようなニュアンスを持つ物質は、アミノカルボニル反応によるものではなく、大部分は、還元的な状態で生成するチオール類(硫黄を含む化合物です)の香りです。 物質としては、2FM(2−フルフリルメルカプタン)で、澱と接触し還元的な状態に長期間置くことで生じます。 瓶内二次発酵のあと、澱と数年間接触するあいだに出てきます。 ボルドーのグランクリュ赤ワインで樽内MLFをすると出てくる香りでもあります。 下記、ネットで検索するとヒットする記事です。 参考までにURLをつけておきます。 http://harmonie.hamazo.tv/d2008-02-09.html もちろん、シャンパーニュの中でアミノカルボニル反応も起こるとは思いますが、糖の量がそれほど多くない(ビン熟の期間の相当の期間は、ドザージュ前ですので、それほど糖分は多くない)ので、色が茶色っぽくなるほどの強い反応ではないと思います。
回答者:安蔵光弘ページのTOPへ戻る
海中では、10メートルもぐると水圧が1気圧上がります。 今我々がいる地上の気圧は1気圧ですので、10メートルの海の中は2気圧ということです。40メートルもぐると5気圧になりますので、シャンパンの中の圧力とつりあうことになります。 シャンパンのコルクを開けるときの力は、(1) コルクを回す時の摩擦力 (2) コルクをまわした後の抜く時の力、の二つに分けられます。 (1) の方の力は、コルクをひねる時の摩擦力なので、地上と同じくらい力は必要だと思います。 (2) の方の力は、地上でシャンパンの栓を抜くときは、シャンパンの内圧が栓をあけるのを手伝ってくれます(中から押し上げます)が、海の中ではこの分の圧力が水圧で相殺されてしまうので、通常よりあけにくいと思います。 また、(もちろん試したことはないのですが)40メートルの深さの海中では、「上手く栓が抜けても、内圧と水圧がつりあっているので、栓は飛ばない」と思います。
回答者:安蔵光弘ページのTOPへ戻る
結論から言いますと、ブドウ果実由来のポリフェノールと樽材から溶出するポリフェノールの呈味の違いは、“種子”由来のプロアントシアニジンの荒々しい渋み・収斂味以外には指摘することが困難なので、樽香の強いワインにおいて「この渋みには樽材が寄与している」と言えても、「このソフトな渋みは樽材由来のポリフェノールに由来するものである」とは断言できません。 ワインの渋みは、一般に「タンニン」と言われている「ポリフェノール(化合物)」によるものですが、1990年代に入ってから、研究者や醸造技術者は化学式や構造式に基づいて分類した名称、すなわち「ポリフェノール」を優先して使用し、それまで広く用いられてきた「タンニン」という名称を使用する頻度は減ってきています。 ワイン中のポリフェノールは加水分解反応が生起しない「縮合型ポリフェノール(縮合型タンニン)」と、加水分解反応が起こる化学的性質をもっている「加水分解性ポリフェノール(加水分解性タンニン)」に大別されます。 ブドウの果実に存在するポリフェノールのうち、「縮合型ポリフェノール」に属する「プロアントシアニジン」、特に種子由来のプロアントシアニジンは、果皮由来のプロアントシアニジンと構造式が異なり、果皮由来のプロアントシアニジンよりも荒々しい渋み・収斂味を呈します。ゆえに果皮・種子・果汁を一緒にして「醸し(かも)発酵」を行う赤ワインの方が、果汁のみで発酵させる白ワインよりも渋味・収斂味が強い訳がおわかりいただけると思います。 プロアントシアニジンは長期間にわたる熟成を経て、加水分解とは別の反応により構造変化が起こり、荒々しい渋みが丸みに変化します。この構造変化の詳細については、現在も研究が進められています。最近、ボルドー地方では、メルローを原料ブドウとした赤ワインの醸造において、発酵に先立って「低温醸(かも)し」を採用することによって、プロアントシアニジンに構造変化を起こさせ、荒々しい渋み・収斂味を柔らかな渋みに変え、早飲みタイプの赤ワインに仕上げることが広く採用されています。この方法だと、熟成に要する年数が短くなる反面、「ワインの寿命」が短命になることは避けられません。 一方、果汁と樽材に含まれるポリフェノールは、「加水分解型ポリフェノール」が主体であり、ブドウの果皮や種子に含まれるプロアントシアニジンのような荒々しい渋みは呈しません。樽熟成中に樽材から溶出する加水分解型ポリフェノールは、果汁中の加水分解型ポリフェノールとともに熟成期間中に加水分解され、分子量の小さなポリフェノールとブドウ糖に、さらにエステルに変化し、複雑な風味を構成します。なお、果皮・種子中にも加水分解性ポリフェノールが存在することはいうまでもありません。
回答者:戸塚 昭ページのTOPへ戻る
オ−トリ−ゼ香というのは、シュ−ル・リ−などの場合に、酵母が自己消化して溶出する様々な成分による香りで、これがワインの旨味や香りの増加に貢献しています。
溶出成分の中で、一番注目されるのは、酵母細胞中の蛋白質が分解してできる、約20種類位のアミノ酸で、このアミノ酸の中でも硫黄を含んだ含硫アミノ酸である
“システイン”が、オ−トリ−ゼ香に関係しています。
ワインの発酵終了期、“システイン”は還元状態(空気に触れていない状態)で、まず硫化水素になります。温泉などで感じるイオウ臭です。この硫化水素は、酸素と触れ合わせる(マクロ・オキシデイションなどの方法で)ことで、“ジエチルサルファイド”に変化します。ご質問にある香りは、この部分だと思います。テイステイング用語で表現している「ミネラル」、「フリンティ」などです。青海苔や塩気を含んだ海風、海草をイメージすると良いと思います。ちなみにフリンティ−(flinty)は、火打石を打った時のニオイ、線香花火のような香りで、これは、化学的には二酸化硫黄の香りで、硫黄を空気中で燃やした時に、発生する香りです。
ここからはニオイの消去に関するものです。
“ジエチルサルファイド”は強い還元力を持っており、魚介類の臭味(アミン類)を消去してしまいます。 アミン類の臭気(ジエチルアミンやトリメチルアミン)は、ビタミンCやクエン酸などを含むレモン果汁によっても消去されます。
レストランでカニやエビの殻をじかに触って中身を取り出し、手に残った魚介臭を、40度位に温めたボ−ル水の中の輪切りレモンで、手を洗い臭味を消すことと同様の効果です。この場合、ビタミンC(アスコルビン酸)は、還元力とその酸で、またレモン中のクエン酸は、アミン類と反応して、無味無臭の成分になります。
生牡蠣にレモンをかけてから、ミネラル香の強いシャブリ・グラン・クリュやプルミエ・クリュと合わせると、生牡蠣中の乳酸がレモンのクエン酸でマスキングされると同時に、料理とワインの酸味も一致させます。
クエン酸とミネラルは牡蠣の内部にある、僅かな臭味も、あっと言う間に消し去ります。またポン酢のような柑橘系醤油(クエン酸と乳酸)は生牡蠣のたれとしてよく使われ、シャブリと味わう時は、調味料を加減よく振りかけると、天下一品の味わいになるのです。
回答者:渡辺 正澄ページのTOPへ戻る
ワインの鉄含有量ですが、抜栓あるいは開栓せずに瓶の外側からする測定することは不可能です。過去の報告に見られるワイン中の鉄含有量は0.1mg/Lから55mg/Lと幅が広く、しかもワインの種類や産地とも関係ありません。1mg/Lという量はワイン5,000L(750ml瓶 約6,667本相当量)にコーヒーショップ備え付けの砂糖の袋(5g詰)1袋を添加したという、ごくわずかな量です。 ワイン中に含まれる鉄等の金属類の混入源は土壌中の金属がブドウ果実に集積されたものや、醸造工程において醸造機器から溶出したもの等があり、その源は一元的ではありません。 土壌中の鉄はブドウ樹の根から吸収され、やがてブドウ果汁に蓄積され、さらに果醪へ移行します。また、ブドウ果汁やワインはリンゴ酸、酒石酸、クエン酸、乳酸といった有機酸を0.5〜1%程度含んでいます。そのため、鉄がむき出しだったり、錆びた部分のある醸造機器や容器を用いると、その個所から鉄が溶け出し、果汁やワインに鉄汚染をもたらします。 ブドウ果汁中の鉄や鉄汚染により果汁中に移行した鉄は発酵中に酵母菌体に取り込まれたり、リン酸など他の成分と結合して不溶性となり、滓となって沈降します。ただし、鉄含有量の多い場合やワインとなった後に醸造機器等から混入した鉄はワイン中に残留する割合が高くなります。 鉄がむき出しの器材や容器が減り、鉄の部分をテフロンやビニール等でコーティングしたり、ステンレス製のものが一般化するにしたがい、器材や容器からの鉄の混入は減少しています。甲州種ワイン中の鉄含有量は20年程前までは10mg/Lを超えるものも見られましたが、現在では平均で0.8mg/Lまで減少しています。 なお、昨今、市場でもてはやされている“無ろ過ワイン”では、微細な滓に吸着された鉄をろ過によって除去することなく瓶詰されるので、出荷時にろ過を行ったワインよりも鉄の含有量の高いワインになることは避けられません。 参考文献:田中隆幸:ワイン中の鉄は、魚介類とワインの組み合わせにおける不快な生臭み発生の一因である, 日本醸造協会誌, 105, 139-147(2010)
回答者:戸塚 昭ページのTOPへ戻る
ワインの試飲会などで「このニオイはビオ臭じゃない?」などという発言が聞かれるようになって久しいような気がします。「ビオ臭」なる言葉の言い出しっぺは一体誰なのでしょうか。困ったことに「ビオ臭」なるものの定義は「ワイン醸造学」の書物に記述されていません。当然のことながら、エノログ(ワイン醸造技術管理士)がきき酒の際に用いる技術用語でもありません。「自然派ワイン」と同様、厳密な定義がされていない「無責任な造語」としか言いようがありません。
インターネットで「ビオ臭」にアクセスしてみると、「ビオ臭」ではなく「ビオ香」と称賛する人さえいるので、なお分からなくなってきます。ある人物の発言を借りれば「ビオディナミ農法で造ったワインに共通して感知されるニオイ」ということですが、これまたどのようなニオイを言っているのかよくわかりません。
「自然派ワイン」なるものをきき酒してきた私の経験からいうと、お世辞にも「ビオ香」と褒めちぎるほどのニオイに遭遇したことはないので、「ビオ臭」について考察をすすめることにします。最初にお断りしておきますが、「臭」というのは「欠陥をあらわす臭い」になります。
1)「ビオ臭」ってフェノレ?
まず考えられるのは、野生酵母であるブレタノマイセスが生成する「フェノレ」といわれるニオイではないか、と思われます。
これを「馬小屋臭」という人がいますが、その様に表現する人の全てが馬小屋(厩舎)のニオイを嗅いだことがあるのか疑問です。大井競馬場や世田谷の馬事公苑の近くへいっても、昔のような強烈な馬小屋臭はしません。周辺住民の生活に配慮した結果と思われます。
厩舎のニオイを嗅いだ経験のない人には「革製品を水で濡らした時のニオイ」と言ったほうが、「馬小屋臭」よりもわかりやすい例示だと思います。
2)「ビオ臭」って還元臭?
次に考えられるのは、いわゆる「還元臭」です。「還元臭」とは硫黄系の臭い、ゆで卵の黄身のニオイと定義されていますが、これは一般のワインでも発生することがあります。
3)「ビオ臭」ってシェリーの匂い?
シェリーといってもいろいろなタイプがあるので、一概には言えませんが、二酸化硫黄(亜硫酸)を使用しないか、使用してもその量が少ないとすれば、アルコールが酸化して生成したアセトアルデヒドに代表されるツンと刺すような刺激的なカルボニル化合物のニオイ、あるいは生成したアセトアルデヒドがアルコールと結合したアセタールという化合物の甘いニオイを言っているのでしょうか。
4)「ビオ臭」って高温劣化臭?
「自然派ワイン」の醸造場は、発酵温度はもちろん貯蔵中のワインの温度管理も「自然のなすがまま」という人がいますが、それならばワインが高温に遭遇した時に生成する焦げ臭やカレーのニオイに類似したジエステル化合物やツンと刺すような刺激的なカルボニル化合物のニオイでしょうか。
5)「ビオ臭」って貴腐ワインの匂い?
ビオディナミ農法による白ワインのなかに貴腐ワインに共通のニオイを感知することがあります。ときには赤ワインにも感じることがあります。これが「ビオ臭」でしょうか。雑草が生えたままの風通しの良くない圃場では、収穫期に一雨あれば、ブドウ果実に貴腐菌(ボトリティス・シネレア)が容易に繁殖します。貴腐ワインに存在するニオイがビオディナミ農法によるワインに感知されても不思議ではありません。貴腐ワインの香りを構成する代表的な成分には酢酸エチルがあげられます。
6)「ビオ臭」って産膜臭?
「自然派ワイン」といわれる赤ワインの中には、マニキュアの除光液と同じニオイがするものがあります。このニオイは接着剤の商品名を借りて「セメダイン臭」といわれることもありますが、原料ブドウ果の貴腐菌(ボトリティス・シネレア)による汚染以外に、貯蔵中のワインの表面に産膜性酵母が繁殖し生成した酢酸エチルによることが多いようです。「ビオ臭」とはこのニオイなのでしょうか。女性には馴染みのあるニオイのためか、酢酸エチル臭に感激する人がいても当然かもしれませんが、ワイン貯蔵管理技術が悪い見本と言えます。
7)「ビオ臭」って酵母自己消化臭?
「自然派ワイン」醸造場では生成ワインの貯蔵温度管理が「自然任せ」というところが少なくありません。発酵終了後のワインをタンクや木桶に移動しても、ワインの品温が高いと酵母が容器の底になかなか沈降せず、滓引きが遅くなります。滓引きが遅れると酵母が自己消化して、いわゆる酵母製剤に感知される「酵母臭」を発現します。このニオイを「ビオ臭」と思っている人もいます。
8)「ビオ臭」って酸臭?
「自然派ワイン」のなかには、鼻にツンとくる食酢に感知される「揮発酸」のニオイがするものがあります。揮発酸は酢酸菌汚染により生成したものと、発酵初期の果醪において糖分が多い時点で果醪の品温が高騰し酵母が生成するものとがあります。このニオイを「ビオ臭」と言う人が少ないのは、酢酸のニオイを日常的に経験しているからでしょう。
9)「ビオ臭」ってジアセチル臭?
赤ワインには発酵バター、海外のヨーグルト、ウオッシュタイプのチーズ、日本人に馴染みのあるものとしては「ご飯のすえたニオイ」に共通のジアセチルという化合物のニオイを感知することがあります。「自然派赤ワイン」には往々にしてこのニオイが強く感知されます。ワインにおいては、このニオイはマロラクティック発酵の際、ワイン中のクエン酸から性質の良くない乳酸菌によって生成することが分かっています。そういう点からいえば、ジエステル臭は有力な「ビオ臭」かもしれません。
10)「ビオ臭」ってヨーグルト臭?
日本産ヨーグルトにはジアセチルよりも乳酸とアルコールの化合した乳酸エチルのニオイの方が感知しやすいと思います。「自然派ワイン」にはこのニオイが強いものがあります。これを「ビオ臭」と思っている人もいるようです。
いずれにしても、「ビオ臭」と表現されているニオイは、圃場、醸造場が微生物学的に不潔な環境のもと、あるいは「独りよがり」な醸造技術を用いて醸造されたワイン中に感知されるニオイといえます。
最近は有機農法を採用して栽培した原料ブドウから醸造されたワインの中にも「ビオ臭」を感知しないものが多くみられるようになりました。
くれぐれも「ビオ臭」を感知しないワインは「自然派ワイン」ではない、などと言わないでください。「無責任な造語」の使用は混乱の源だと、私は思っています。
回答者:戸塚 昭ページのTOPへ戻る
今の形が踏襲されはじめたのは、18世紀後半ぐらいからだと思います。
多くの例外はありますが、ボルドーやボルドー系品種はボルドー型、ピノやシャルドネはブルゴーニュ型が使われることが多いですね。
ボルドー品種はカベルネでピノよりはタンニンが多く、オリの量が多かったので、これを沈め上澄みがとりやすい、ボルドー型でしょうか。
また、18世紀後半はボルドーワインも西インド諸島やロンドンに輸出されていたころで、運送時の収まりはボルドー型の方が良いようにも思えます。
また、起伏の多い土地で、どうしても狭いカーブに貯蔵することを考えると、ブルゴーニュ型の方が収納数が増える(瓶口を互い違いにおけば)など実用的な側面もあったのでしょう。
回答者:村上 安生ページのTOPへ戻る
「きいろ香」の特長香は時間とともに減少していきます。またワインはあまり長熟タイプではありません。
ボルドーやロワールのSBでも通常は、フレッシュなうちに飲むほうが美味しいワインが多いと思います。
しかし、SBにもシャルドネほどではなくても、熟成に耐えうるワインもあります。
きいろ香の製造技術として、ワインを非常にクリーンに醸造していますので、通常の甲州ワインよりは、良い熟成をします(瓶の中で)。
たまたま、先日、2006年のきいろ香マグナムを利き酒しましたが、まだまだ若々しく、美味しく飲めました。
恐らく、保存状態が良ければ、2007年は、あと3〜5年は美味しく頂けると思います。
またその後も、柑橘系の香りは少なくなりますが、甲州ワインとして良い熟成を続けると思います。
回答者:味村 興成ページのTOPへ戻る
ワインの知識についてのご質問はこちらまで >> アドレス: